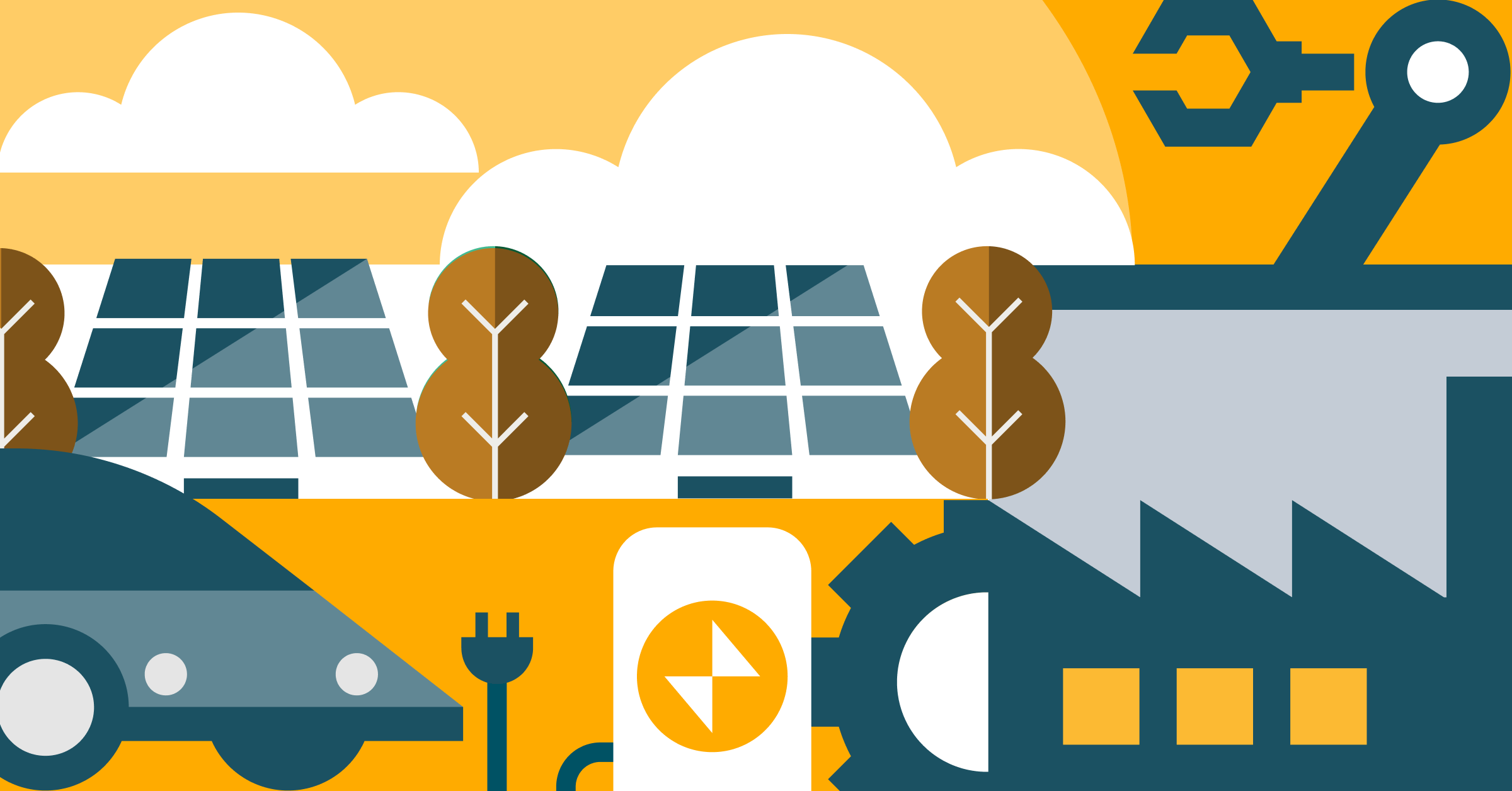レコメンデーションシステムによるプレイヤー体験のパーソナライズ
ゲームがどのようにレコメンデーションシステムを活用して、より豊かでプレイヤー中心の体験を実現しているかを探る

Summary
- パーソナライゼーションを通じてプレイヤーエンゲージメントを促進する:推奨システムがゲーム内体験をパーソナライズする方法を学びます。ミッションやストアフロントからマルチプレイヤーマッチメイキングまで、プレイヤーの満足度とリテンションを向上させます。
- 収益を増やし、LiveOpsを最適化する:インテリジェントな推奨がIAPのコンバージョンを改善し、�マネタイゼーションのタイミングを調整し、ソーシャルマッチングやサーバー選択などのダイナミックなLiveOps機能をサポートする方法を発見します。
- より良いデータでよりスマートで適応性のあるゲームを構築する:高品質なデータ、A/Bテスト、TorchRecのような現代的なMLアーキテクチャが、ゲームスタジオがプレイヤーの行動とビジネス目標に進化するパフォーマントなモデルを訓練する方法を見てみましょう。
はじめに
プレイヤー中心の体験を生み出すうえで最も強力なツールの一つが、レコメンデーションシステムです。これは驚くことではありません。なぜなら、パーソナライゼーションとは究極的には、特定のプレイヤー、もしくはプレイヤーのグループに共鳴する行動・アイテム・コンテンツを提案する技術だからです。レコメンダーは、プレイヤージャーニーのあらゆる段階でパーソナライゼーションを強化する基盤的な機能を担っています。
本ブログでは、ゲームにおけるレコメンデーションシステムの活用方法について掘り下げ、より意義のあるプレイヤー体験の実現方法を探ります。具体的には、マーケティングや収益化からユーザー獲得、さらにはライブオペレーションに至るまで、どの領域で活用されているのかを紹介し、世界中の先進的なゲーム開発者が採用しているベストプラクティスやアプローチを共有します。最後に、実際のユースケースや業界全体での具体的な事例を取り上げ、その効果を明らかにしていきます。
ステージの設定
レコメンダー(推薦システム)は、多くの場合「アクションを提案する仕組み」として考えられています。たとえば、最適なオファーを提示したり、購入を最適化したり、コンテンツやストアのカルーセルを埋めたりする、といった用途です。これらは確かに価値が高く、世界中のプレイヤーに好まれている活用方法です。
しかし、レコメンダーはプレイヤーの嗜好をより深く理解するためにも役立ちます。従来、プレイヤーのセグメンテーションやクラスタリングなどのインサイトは人間の解釈に依存してきましたが、レコメンダーを使えば機械的にプレイヤーの文脈を把握でき、開発者はそれを直接活用してフィードバック対応や製品改善につなげることができます。
プレイヤーの嗜好をより深く理解できれば、ゲーム企業はプレイヤーにとって最も魅力的で価値のある体験に合わせてパーソナライズを行うことが可能になります。つまり、オファーやクエスト、その他のゲーム要素をプレイヤーの関心に沿わせることで、プレイヤー中心の体験を生み出すことができるのです。
よくある質問のひとつに「レコメンダーを導入するとビジネスにどのような成果が期待できるのか?」というものがあります。結論としては、プレイヤーのエンゲージメントを高め、長期的な関係構築を促進することです。
具体的な内容に入る前に強調しておきたいのは、A/Bテスト(カナリアリリースやフィーチャーフラグと合わせて)の重要性です。多くの機械学習(ML)や生成AI(GenAI)モデルと同様に、厳密�なA/Bテスト手法を通じた結果検証は欠かせません。A/Bテストには2つの目的があります。レコメンダーが意図通りに機能していることを確認すること、そして明確なビジネスインパクトを示すことです。
A/Bテストを設計する際は、最初に明確な目的と指標を定義しておくことがベストプラクティスです。たとえば「何を増加させたいのか、あるいは減少させたいのか」を具体的に決めておく必要があります。現在、ゲーム業界ではA/Bテストの採用は進んでいますが、依然として明確な仮説を立てずにテストを実施し、その後で指標を確認する傾向が残っています。アウトカムを明確に定義しないと、効果的なテスト設計やレコメンダーの影響を正しく測定することが難しくなってしまいます。
次に、効果的なゲーム内レコメンデーションシステムを構築するために不可欠な「高品質で正確にラベル付けされたデータ」の重要性について見ていきましょう。
レコメンダーにはラベル付けされたデータが必要です
レコメンダーは、適切にラベル付けされたデータセットやメタデータを基盤に構築されると、はるかに効果的に機能します。ラベルの種類は文脈によって大きく異なりますが、特徴量エンジニアリングにおけるベストプラクティスを活用することが重要です。推奨結果と相関しないラベルを含めてしまうと、最低でもモデルのコストが増大し、最悪の場合は推奨の精度を低下させてしまいます。
例を挙げてみましょう。ゲーム内のIAP(課金アイテム)でシャツをプレイヤーにおすすめする��ケースを考えます。そのプレイヤーはこれまでに10枚のシャツを購入しており、9枚が紫、1枚が青で、価格は1ドルから100ドルまでさまざまです。このとき「色」「種類」「価格」という3つのラベルしかなければ、モデルは「紫色が好み」と判断し、青は外れ値として扱い、さらに紫のシャツをおすすめするでしょう。
しかし、実際の購入理由はそこではありません。10枚すべてのシャツに「シャーロック・ホームズ」がデザインされていたのです。つまり、購入を動機づけたのは「色」ではなく「キャラクター」だったのです。この例は単純化していますが、複雑なケースにも容易に当てはめて考えることができます。
もう一つ例を挙げます。あるアーティストが最新作を「SF」とラベル付けしたとします。しかし、プレイヤーの中にはそれを「サイバーパンク」として認識する人もいるかもしれません。その場合、「サイバーパンク」を好むプレイヤーにはおすすめされない可能性があります。ここで活用できるのが、LLMを用いた自動タグ付けです。これにより、ラベルの一貫性を高め、各コンテンツに関連づけられるラベルの種類を拡張することができます。
さて、成果の定義、A/Bテストの仕組み、そして十分にラベル付けされたデータが揃ったところで、次にゲームにおけるレコメンダーの活用方法について見ていきましょう。
レコメンダーはどこで活用できるのか
レコメンダーは一般的に「ストアでのオファー提案」に使われるイメージがありますが、実際にはUI要素のパーソナライズ、プロシージャル生成コンテ�ンツ、マルチプレイヤーマッチの編成、その他さまざまなゲームプレイ要素にも活用できます。根本的には、レコメンダーはプレイヤーに次に提示すべき「最適なもの」――コンテンツ、選択肢、機能――を判断する役割を果たします。
多くのレコメンダー導入は「複数の候補の中からどちらを提示するか」という二者択一から始まります。選択肢が多すぎると、プレイヤーは混乱したり選べなくなったりします。そのため、通常は有望な2〜3個の選択肢に絞り込むことが目標です。では、どれが最適なのか?最初の問いは「プレイヤーにとって影響が大きいのはどれか?」ですが、さらに良い問いは「自分が達成したい成果は何か?」です。推奨を「入力」ではなく「成果」に結びつけることで、モデルをより体系的に設計・検証しやすくなります。
ストアに基づいたレコメンデーションについては多くの議論がありますが、ここでは一旦「ゲームプレイの仕組み」に目を向けてみましょう。
レコメンダーは本質的に短期的な適用に強く、次に購入すべき商品や利用すべきサービスを提示します。しかし「ゲームクリア」「プレイ時間」「デイリーセッション数」といった長期目標に基づければ、短期的な推奨は「ゴールデンパス」となり、プレイヤーを長期間にわたって有意義な進行へ導くことができます。
こうしたパスを構築するには、プレイヤージャーニーを個人レベルと全体のプレイパターンの両面から理解する必要があります。その知見はテレメトリーデータから得られます。例えば、ファネルの離脱率、低い機能利用率、進行ポイント間の異常に長い間隔、あるいはその他の摩擦の兆候です。多くの場合、一部のプレイヤーはそうした障害を突破しますが、別のプレイヤーは苦戦したり離脱してしまいます。その違いを理解することは、より多くのプレイヤーが進行できるよう体験を調整する上で重要なシグナルとなります。
さらに、レコメンダーは本質的に「反復的」なものです。ゲームメカニクスやメタは進化し、新機能が追加され、プレイヤーの行動も変化します。それに応じてモデルも進化し続ける必要があります。時間が経つと、有効なモデルであっても最適な性能から徐々にずれていきます。そのため、継続的な実験が不可欠です。プレイヤーのライフタイムが終わるまで待ってからモデルを更新するのではなく、オフポリシー推奨(現在のモデルが提示しない選択肢をあえて提示する)といった制御された変動を導入できます。もしそれがより良い成果をもたらすなら、新しいデータでモデルを再学習すればよいのです。
補足: 一般的にレコメンダーは「どのコンテンツをプレイヤーに提示するか」を決めるためのツールと考えられていますが、逆のケースもあります。つまり「どのプレイヤーに新しいコンテンツを届けるべきか」を判断する場合です。例えば、限定コンテンツを期間限定でリリースし、1万人だけに提示したいとします。この場合の問いは「プレイヤーに何を見せるか?」ではなく「このコンテンツを提示すべき適切なプレイヤーは誰か?」になります。こうしたケースで��は、過去の行動・嗜好・エンゲージメントの可能性に基づいて、最適な対象を特定するためにレコメンダーを活用できます。
応用例1:プロシージャル生成による目標とミッション
現代のゲームは、プレイヤーに有意義な進行を促すために、多様なミッションや目標、アクティビティを提供できます。しかし、選択肢が増えるにつれ、プレイヤーの興味に合ったものを優先する必要性も高まります。単純なアプローチとしては、プレイヤーが過去に選んだ目標と同じタイプをさらに生成・提示する方法がありますが、それではすぐにゲームプレイがマンネリ化し、探求意欲を失わせてしまいます。過去のプレイヤー行動データに基づく機械学習型レコメンダーを使えば、魅力に欠ける、あるいは重複したミッションデザインを回避できます。
例えば、多くの基本無料ゲームに共通する「デイリー目標」機能を考えてみましょう。基本的な構造(例:目標を達成して報酬を獲得する)は同じでも、その具体的な内容はプレイヤーの嗜好の変化に合わせて調整できます。あるプレイヤーはアイテム収集を好み、別のプレイヤーはPvPバトルやユニットのアップグレードを楽しむかもしれません。多様でバランスの取れたデイリー目標の組み合わせは、プレイヤーにゲームのさまざまな側面に触れる機会を与えます。
また、プレイヤーが進行するにつれて、モチベーションも変化します。最初はアップグレードが動機になっていても、そのうち競争やソーシャル要素、戦略性を求めるようになるかもしれません。あるいは、ゲーム内通��貨(ハードカレンシー)の価値を伝えるタイミングに差しかかることもあります。レコメンデーションシステムはこうした変化に適応し、プレイヤーの行動やエンゲージメントパターン、過去の目標達成度に基づいて、新たな進行ルートを示す目標を提案できます。
うまく実装されれば、「デイリー目標」のような一見飾り的な機能も、リテンションを高め、プレイヤーの感情的・金銭的な投資を促進する戦略的な資産となります。プレイヤーにとって関連性の高い目標を提示することで、小売業が「適切な商品を適切な人に、適切なタイミングで提示」することでコンバージョンを高めるのと同じように、ゲームでもエンゲージメントを深められるのです。ゲームにおける「商品」はプレイ体験そのものであり、最適なプレイ体験を提案することによって、プレイヤーの楽しみを強化し、ゲーム自体との長期的な結びつきを生み出すことができます。
データ・インテリジェンスが業界を再構築
応用例2:ストアフロントとオファー
ゲーム内のコマース体験をパーソナライズすることで、IAP(課金アイテム)収益や収益全体に即時的な改善をもたらすことができます。重要なのは「適切なタイミングで適切な価値を提供する」ことです。これらはレコメンデーションエンジンによって最適化することが可能です。
多くの基本無料ゲームにおけるマネタイズモデルは、0.99ドルから100ドル超まで幅広い価格帯をカバーしています。この幅広さが課題となります。すなわち、プレイヤーにとって選択肢が多すぎるのです。レコメンダーは選択肢を絞り込み、コンバージョンにつながる可能性の高いものを提示できます。
コマース向けレコメンダーは、ゲームプレイのパーソナライゼーションに使われるのと同じテレメトリーデータやプレイヤー行動データを活用できますが、現実世界の指標も組み込むことがあります。デバイスの種類、地域の所得データ、ゲーム内フレンドの消費行動といったシグナルを組み合わせることで、プレイヤーの可処分所得や支出意欲・支出可能性を推定できます。たとえば、最新ハードウェアを使用している裕福な地域のプレイヤーには高額バンドルが効果的である一方、別のシグナルを持つプレイヤーには1〜10ドル程度のオプションの方が好まれるかもしれません。
多くのレコメンデーションエンジンは「何を提示するか(What)」に焦点を当てていますが、「いつ提示するか(When)」も同じくらい重要で�す。特にLiveOps、GaaS、モバイルゲームではその重要性が高まります。オファーは往々にして時間依存的であり、適切なタイミングで提示することで、プレイヤーの無関心や「常にオファーがあることによる疲労感」を打破できます。モデルは、例えば「試合に勝つ」「レベルアップする」といったイベントが、プレイヤーの最初または最頻のIAP購入に先立つ傾向を分析し、最適なトリガーモーメントを特定して、ストア訪問を促す招待をゲーム内で提示できます。
補足: 季節イベントやマクロ経済の動向も消費行動に影響します。ホリデーシーズンには支出意欲が高まり、不況時には低下するかもしれません。そのため、コマースモデルは常に再学習・検証を行い、最新の状況に適合させる必要があります。
応用例3:マルチプレイヤーマッチ
レコメンダーは、プレイヤー同士をマッチングする際にも活用できます。これは一回限りのマルチプレイヤーセッションだけでなく、ギルドやクランといった持続的なソーシャル構造の形成にも役立ちます。
基本的なマッチメイキングは、スキルレベルや接続品質を基準にして、公平で快適なプレイ体験を保証します。特に競技性の高い対戦では、プレイヤー数が少ない場合も多く、接続範囲を制限したELOマッチングシステムが一般的です。一方、カジュアルや混沌としたマルチプレイ形式では、スキルよりもマッチングの速さや接続の安定性が優先されることがあります。
しかし競技的なバランスを超えて、レコメン��ダーは「社会的な相性」も高めることができます。思い出深いマルチプレイ体験を振り返ってみてください。その多くは、ゲームの仕組みそのものよりも、一緒に遊んだ仲間によって形作られているはずです。プレイスタイルや装備、その他の属性を理解することで、マッチメイキングアルゴリズムは、補完的なチームメイトや、非対称的な(良い意味での)対戦相手を作り出すことが可能になります。
モデルが高度化すると、プレイヤープロファイルにはELOを超えた細かな特性が含まれるようになり、それらがリアルタイムでマッチメイキングに利用されます。ここで課題となるのは「マッチの質をどう測定するか」です。プレイヤーに試合を評価してもらう方法もありますが、より客観的な指標としては、1日のセッション回数の増加、週あたりのプレイ日数、フレンドとのプレイ時間、ボイスチャットやコミュニケーションの利用度など、継続的な社会的エンゲージメントを示す兆候が挙げられます。
どの成果指標を選ぶにしても、それは長期的かつ一貫したプレイヤーエンゲージメントの向上と関連づけられるべきです。測定可能な成果があれば、それに基づいてモデルのA/Bテストを行い、最も効果的な手法を見つけることができます。(もちろん、地理的に十分なプレイヤー母集団が存在し、接続状況や言語、タイムゾーンの差異が結果を損なわないことが前提となります。)
例えば、過去のチャットメッセージやボイスチャット、好みの言語を利用して、円滑にコミュニケーションが取れる、いわゆる「一緒に遊んでいて心地よい」プレイヤー同士をマッチングすることができます。別のケースでは、限られたプレイ時間しか取れないプレイヤー(たとえば新米の親など)が、ハイペースなチームでは苦戦するものの、同じような参加ペースのグループでは楽しめる、といったソーシャルマッチングのメリットもあります。
さらに、課金行動も重要な要素です。高額課金者のグループは、経済的についていけないプレイヤーを疎外してしまう可能性があり、逆に課金の見込みがあるプレイヤーが無課金層に混じると場違いに感じることもあります。時間的・金銭的な投資に多少の差があることはグループのパフォーマンスを高める場合もありますが、大きな差は無意識的にでもモチベーションを下げてしまうのです。したがって、同程度のエンゲージメントや経済的状況を持つプレイヤー同士をマッチングすることで、より快適で長続きするゲーム体験を実現し、コミュニティ全体の成長にもつながります。
ゲームにおけるレコメンダーの活用例
プレイヤーセントリックな体験
先に述べたように、レコメンダーはプレイヤーの嗜好に合わせることで、エンゲージメントを最大化し、継続的にプレイしてもらうと同時に「大切にされている」と感じてもらうことが重要です。以下では、現在各社の開発者がレコメンダーをどのように活用しているかを紹介します。
開発者のストーリー:2K Games
Data and AI Summit 2025 の Games Industry Forum にて、2K Games の Sports 部門GMである Dennis Ceccarelli 氏が、同社におけるレコメンダーやパーソナライゼーション��の取り組みについて共有しました。特に興味深かったのは、プレイヤーを「ゴールデンパス」に導くために、ヒントや報酬を仕組みとして活用していた点です。2K Games では、プレイヤーの体験、過去のプレイヤー行動、明確に定義された成果といった情報をインプットとして取り込み、プレイヤーが高いエンゲージメントを維持し、パーソナライズされたゲーム体験を楽しめるように工夫しています。
「ゴールデンパス」という概念はゲームにおいて非常に重要ですが、その意味は多様で、すべてのゲームに共通する単一のゴールデンパスが存在するわけではありません。むしろ、ひとつのゲームの中でも複数のパスがあり得ます。そこで、レコメンデーションモデルのテストを、ビジネス指標やKPI、成果といった下流の指標に結びつけることで、プレイヤーを最終的な「ゴールデンアウトカム」へ導くために、どの中間地点を推奨すべきかをより的確に判断できます。
そのアウトカムとは、日次の継続的なエンゲージメント、プラチナランク到達、メインストーリーのクリア、あるいは長期的な課金プレイヤーへの転換など、ゲームやプレイヤーごとに異なります。
プレイヤーを理解する
レコメンダーは、Player360 の取り組みを強化する強力な手段です。この文脈における目的は、すぐにアクションを促すことではなく、プレイヤー一人ひとりを包括的に理解することにあります。この基盤が整えば、ゲーム体験のさまざまな場面で、より迅速かつ精度の高いレコメンドを行えるようになります。幅広い指標に基づいてプレイヤーの嗜好を分析することで、新しい機能を解放したり、複数のユースケースをサポートすることが可能になります。
では、K-Meansクラスタリング、セグメンテーション、レコメンデーションシステムのどれを使うべきなのでしょうか?答えは基本的に「はい」ですが、その理由はそれぞれ異なります。各アプローチは異なる目的に適しています。セグメンテーションは、人間が理解しやすい大まかなグループ分けが必要な場合に理想的です。特に「人間の意思決定プロセスが関わるケース」において有効で、地理、人口統計、コホート、プレイ時間といった属性でプレイヤーを分類できます。こうしたセグメントは、チームがキャンペーンを計画したり、行動を分析したり、戦略的な意思決定を下す際に役立ちます。
一方、自動クラスタリング(例:K-Means)の出力は、人間が直感的に理解するには難しい場合があります。従来は、クラスターに名前を付け、マーケティングやリマーケティングの具体的なユースケースに落とし込むのに多大な労力が必要でした。このプロセスを効率化するために、LLMアシストクラスタリング支援が用いられることがあります。これにより、自動生成されたクラスターの違いを説明でき、プロジェクトの期間を数か月から数日、さらには数時間にまで短縮することが可能です。
最近では、人間の介入を完全に排除し、マーケティングコンテンツ生成に自動クラスタリングを利用する試みも増えています。これらの手法では、LLMや生成AIを活用し��て、パーソナライズされたリマーケティングコンテンツを大規模に生成します。
もしあなたのゲームが多様なモードやユーザー生成コンテンツ(UGC)を含んでいて、プレイヤーのエンゲージメントを高めたいのであれば、レコメンデーションシステムが最適な解決策となることが多いです。これらのシステムは、セグメンテーションやクラスタリングの出力を特徴量として取り込み、行動データに基づくグルーピングとリアルタイムシグナルを組み合わせることで、効果的な提案を行うことができます。
プレイヤーベースの拡大
ユーザー獲得やマーケティングにおいて、レコメンダーは幅広い用途があります。一般的な目的は、プレイヤーの嗜好を把握し、コホートや類似オーディエンスを構築してキャンペーン戦略に活かすことです。これにより、クリエイティブやメッセージング、クロスセルの機会、広告ネットワークでのターゲティングに至るまで活用できます。
ユーザー獲得最適化のユースケース
マーケティングクリエイティブとターゲティングUA
高LTVプレイヤーに響くマーケティブを制作する際、レコメンダーはそのオーディエンスに最も訴求するトップ3の機能・マップ・ゲーム内体験を抽出するのに役立ちます。これらのインサイトは、ユーザー獲得キャンペーンにおけるクリエイティブ開発やオーディエンスターゲティングを導くことができます。
リマーケティング
このユースケースはターゲティングUAに似ています�が、目的は異なります。新しい類似グループに訴求するのではなく、既存プレイヤーの再エンゲージメントを狙うものです。以前に触れたように、セグメンテーションはアーキタイプに基づいたプログラムを通じてリマーケティングを支援します。さらに一歩進めると、レコメンダーはLLMと連携し、プレイヤーごとにパーソナライズされたメッセージを生成できます。これにより、一貫したフレームワークに沿いながらも、個々のプレイヤーの嗜好に適応した「ほぼ1対1」のコミュニケーションが可能になります。
ハイパーカジュアルゲームのクロスマーケティング
モバイルやWebベースのハイパーカジュアルゲーム開発者であれば、平均2〜3日でプレイヤーが離脱してしまうという短いライフサイクルに直面しているはずです。目標は、エンゲージメントを最大化し、十分な広告を配信して高いROAS(広告費用対効果)を達成し、さらにポートフォリオ内の別タイトルへとプレイヤーを誘導することです。レコメンダーは、プレイヤーが現在のゲームから離脱する直前のタイミングで、次に最適な2〜3タイトルを特定できます。これにより、エコシステム全体でプレイヤーのライフタイムバリューを拡大できるだけでなく、プレイヤーごとに最大限のROASを引き出すことができます。
開発者インサイト:SciPlay
SciPlay にとって、マーケティングは成長のエンジンです�。ユーザー獲得コストが上昇する中、重要なのは「より多く費やすこと」ではなく「より賢く費やすこと」になっています。マーケティング業務やキャンペーン戦略にインテリジェントなレコメンデーションモデルを組み込むことで、予算配分を大きく見直し、潜在的価値が最も高いプレイヤーを戦略的に特定できるようになりました。このデータドリブンなアプローチにより、投じる1ドルすべてがより効果的に機能し、極めて競争の激しい環境においてもプレイヤーの質とROIを改善することができています。
業界パートナーインサイト:Braze
世界中のゲーム企業に利用されているカスタマーエンゲージメントプラットフォームのリーダーである Braze は次のように語っています。
「カスタマーエンゲージメントプラットフォーム内でのレコメンダーシステムは、強力なリエンゲージメント手法を提供できます。プレイヤーを再び引き込み、興味を再点火させるよう設計された高度にパーソナライズされたジャーニーを導くことができるのです。プレイヤーのエンゲージメントが低下してきた際には、レコメンダーがそのプレイヤーのゲーム内履歴、好むコンテンツ、さらには過去にどのコミュニケーションチャネルに反応したかまで分析します。こうした包括的なインサイトによって、提示すべき最も関連性の高いコンテンツ(例:新しいゲーム機能、別タイトル、特定アイテム、ソーシャルイベント)や、最適なインタラクションの順序とメッセージ配信方法(送信のタイミ�ングやプレイヤーに最も効果的なチャネル)を判断します。
このようなリエンゲージメントキャンペーンにおけるインテリジェンスは、プレイヤーの進行を動的にパーソナライズするために活用できます。たとえばキャンペーンの重要な分岐点において、レコメンダーモデルは特定のプレイヤーがどの分岐やメッセージシーケンスに最も反応・転換しやすいかを予測します。そして、そのプレイヤーを個別のジャーニーに沿った最も効果的なルートへとインテリジェントに誘導するのです。
例えば、競技モードに熱心だが離脱の兆候を見せているプレイヤーを考えてみましょう。リエンゲージメントキャンペーンでは、競技的な新しいチャレンジを強調するルートと、ソーシャルギルドイベントに焦点を当てるルートの2つを用意します。カスタマーエンゲージメントプラットフォーム内のレコメンダーシステムは、そのプレイヤーが「ゲームX」に興味を持ち、過去にゲーム内アラートを好んでいたという情報を特定します。
キャンペーンにプレイヤーが入った瞬間、レコメンダーはそのプロフィールを評価し、最も効果的と予測される「競技的チャレンジ」のルートへと自動的に誘導します。さらに、そのルート内のメッセージも(AIの支援を受けて)個々のプレイヤーにとって独自に関連性の高いものとして調整することができるのです。」
収益の拡大
レコメンダーが活用される領域の中でも、収益成長は最も広く浸透している分野であり、その理由は明確です。ゲームにおいて、エンゲージメントの向上は通常、収益の向上につながります。レコメンダーは、ゲームが提供する価値を、その価値を最も享受しやすいプレイヤーに結びつける役割を果たします。
レコメンダーが収益に与える影響は、あらゆる業界で確認されています。デジタルコマースの時代以前から、物理的なレコメンドの類似例は存在していました。例えば、スーパーマーケットでおむつとビールを並べて陳列する、といったものです。これは単なる巧妙なマーチャンダイジングではなく、原始的な「レコメンド」──すなわち「これを買った人は、あれも買っています」という発想でした。
具体的なユースケースに入る前に押さえておきたいのは、レコメンダーには単純なヒューリスティックから高度な機械学習モデルまで、さまざまな形態があるということです。基本的な仕組みでも十分に成果を出すことができます。多くの開発者はシンプルに始め、より高いリターンを求めて徐々に複雑さを増していきます。本ブログではMLベースのレコメンダーに焦点を当てていますが、最も重要なアドバイスは「まずは何か取り組むこと」です。プレイヤーにコンテンツを提示する方法を少し改善するだけでも、収益に大きなインパクトを与える可能性があります。
レコメンダーによる収益向上のユースケース
Next Best XXXX
レコメンダーを活用して収益を伸ばす場合、その大半のユースケースは「Next Best XXXX」という形で表現できます。つまり、プレイヤーが次に最も欲しがるものを提案するというのが目的です。最も一般的な例は「Next Best Offer」であり、プレイヤーデータ、アイテムの嗜好、キャラクターの使用状況、過去の購入履歴などから、どの商品(SKU)が最も響くかを判断します。これらは、単一のゲーム内広告、キュレーションされたオファーのカルーセル、あるいはストアの動的な並び替えといった形で提示されます。
購入最適化(Purchase Optimization)
「Next Best Offer」の一部として、購入最適化はプレイヤーが受け入れやすい最適価格のバンドルを見つけることを目的とします。これは、あらかじめ設定されたSKUから選ぶ場合もあれば、オンデマンドでパーソナライズされたオファーを生成する場合もあります。ただし後者は非常に複雑で(個別に商品構成・価格・割引率を決める必要があるため)、大規模に実装されることは稀です。特に、プレイヤー同士がソーシャルメディア上でオファーを比較し始めると「不公平感」が生まれやすく、不満につながるため、多くのスタジオは極端にパーソナライズされたバンドルを避けています。
ストアの並び替え(Store Ordering)
レコメンダーは、ゲーム内ストアの商品を最適な順番で提示する上でも重要な役割を果たします。ある開発者は、過去の購入データやエンゲージメント指標に基づいてストアを並び替えただけで、購入率が20%向上したと報告しています。別の開発者は、プレイヤー向けに500以上のSKUを用意していましたが、1ページあたり9〜12個しか表示できず、複数ページに分散していたため、検索機能があってもプレイヤーが目的の商品を見つけに�くい状況でした。そこで最も効果的だったのは、各プレイヤーに最も響きそうな24商品を優先表示する方法でした。これを2ページに分け、1ページ目に上位12、2ページ目に13〜24をランダムに配置することで、プレイヤーが「常に新鮮さを感じる」ようにしました。このアプローチは商品の発見性とエンゲージメントを高め、ストア全体がよりパーソナライズされ、応答性の高いものに感じられるようになりました。
プレイヤーエンゲージメントとリテンションのためのユースケース
チャーン(離脱)防止
リマーケティングのアプローチを発展させ、ゲーム開発者はインサイトをチャーン防止戦略に統合し始めています。例えば、過去の離脱プレイヤーのデータを用いて、将来的に離脱しそうなプレイヤーを早期に特定できるエージェント型AIシステムがあります。プレイ頻度やセッション時間の変化など、似たような傾向や行動変化を検出することで「離脱予備軍」とマークし、リマーケティング用の仕組みを活用して、LLMで生成したパーソナライズされたメッセージを送信し、再エンゲージメントを図ることができます。
体験のパーソナライゼーション
レコメンダーの最先端の活用例は、ゲーム自体への統合です。たとえばオープンワールドゲームでクエストを終えた直後、「次はどのクエストをやるべきだろう?」と考える場面を想像してみてください。メインストーリーを進めているなら次の章へ進むのが自然ですが、サイドクエストの場合は続きがないこともあります�。その場合、「近くのクエストを選ぶ」「途中で止まっているものを再開する」「特定の敵を倒す」といった選択肢が考えられます。ここでレコメンダーを組み込むことで、プレイヤーの好みに沿った次の最適なクエストを提示し、長期的なエンゲージメントを維持できるのです。
新コンテンツ問題
このアプローチは、未検証のコンテンツ全般に適用できます。新しく追加されたSKU、ユーザー生成アイテム、全く新しいゲームモードなどです。こうしたケースでは、多くの開発者が「探索(explore)と活用(exploit)」の両モデルを組み合わせ、短期的な成果と長期的な発見をバランスさせています。
Exploitモデル は、安定してエンゲージメントを高める実績あるコンテンツを優先的に提示するため、迅速な成果を出しやすく、多くの開発者が採用しています。ただし、新規やあまり知られていないコンテンツを表に出すことは苦手です。
Exploreモデル は、新しいコンテンツを試しに提示する役割を持ちます。たとえば、一部の開発者はストアやUIでカルーセルを2段に分け、1段目には「実績あるコンテンツ(exploit)」を、2段目には「新規・未知のコンテンツ(explore)」を配置することで、発見性を高めています。
Exploit型レコメンダーは価格・説明・購入タイプといった基本的な属性に基づきます��が、Explore型は色、テーマの使い方、トーンなど追加のシグナルも考慮します。これにより、十分な行動データが集まる前の段階でも「どのプレイヤーがこの新コンテンツに興味を持つか」を賢く予測でき、コンテンツ発見と実績検証の橋渡しが可能になります。
開発者の洞察:SciPlay
リテンションは新たな獲得です。失われた高品質のプレイヤーは、高額なUAキャンペーンを通じて将来的に回収しなければならないコストです。そのため、SciPlayは予測的な離脱モデルに大きな投資をしています。これはプレイヤーがいつ離れるかを特定するだけでなく、彼らがその地点に達する前にパーソナライズされた介入で彼らを引きつけるためです。このようなモデルは私たちの精度を10倍以上に向上させ、良い意図を持ったリテンション努力が実際には逆効果になるというミスターゲティングの落とし穴を避けるのに役立ちました。最終的には、適切な経験を適切なプレイヤーに適切な瞬間に提供することが重要です。
レコメンデーションを用いてより良いゲームを作る
ゲーム開発者はレコメンデーションシステムを「ローンチ後の付加機能」としてだけでなく、開発サイクル全体を通じた戦略的なコンポーネントとして捉えるべきです。特に GaaS や LiveOps 環境においてはその重要性が高まります。
ゲームプレイ体験の形成から、マネタイズやパーソナライゼーションの設計に至るまで、レコメンダーはより良く、より適応的なゲームを構築するための重要な要素になりつつありま��す。多くのユースケースはプレイヤー体験や収益最適化に分類されますが、中には開発リスクを軽減することを直接支援するものもあります。
以下の3つのユースケースは、開発プロセスにインテリジェントな柔軟性を導入し、チームが大規模なデザインや制作判断に踏み切る前に、コンテンツをテスト・適応・調整できるようにします。
開発リスクを軽減するユースケース
ゲームバランス
開発ライフサイクルを進める中で、フレンズ&ファミリー、アルファ版、ソフトローンチ、グローバル展開といった段階を経ても、ゲームバランスの調整は常に必要な取り組みです。
難易度マッピング
シンプルなパズルゲームのように難易度が比較的一次元的な場合、ヒューリスティックを適用できます。しかし、遭遇戦がプロシージャル生成されるようなダイナミックなゲームでは、レコメンダーの役割が一層興味深くなります。プレイヤーの過去の遭遇データに基づいて、「勝率XX%となる適切な構成」とは何か?その遭遇に含まれるべき敵の種類、地形、武器の入手可否、回復ポーションの有無などを調整し、特定の目標を達成できるよう設計するのです。
ソフトローンチにおけるコンテンツ誘導
これは「Next Best XXXX」アプローチの派生ですが、ゲーム開発ライフサイクル全体を通じて重要です。既存タイトル向けに新しいコンテンツを開発したり、プリプロダクション中のゲー�ムに新機能を導入したりする際には、プレイヤーに新しいシステムへのエンゲージメントを促す必要があります。従来はメール、動画、キュレーションされたクエストなどがよく利用され、一定の効果を発揮してきましたが、これらは往々にして一律的で静的な手法です。レコメンダーを活用すれば、プレイヤー一人ひとりにより深く響く新コンテンツへと誘導しやすくなります。
改善されたゲームプレイのためのLiveOperationsの最適化
最後に紹介するユースケースは、LiveOperations(LiveOps)の領域に属します。これは動的かつリアルタイムで適用されるもので、パーソナライズされたプレイヤー中心の体験を優先し、継続的なゲームプレイをより豊かにすることを目的としています。
以下は、レコメンダーを活用して開発者がより魅力的で応答性が高く、個別化されたゲーム体験を提供できる、代表的なLiveOpsユースケースです。
LiveOps内のレコメンダーのユースケース
フレンド/ソーシャルレコメンダー
ゲーム内に有意義なソーシャルエンゲージメントを取り入れることは、プレイヤーのリテンション向上に効果的です。実際、ネガティブなやり取りであってもリテンションは改善するといったフィードバックもありますが、本当に効果的で健全なのは「有意義なつながり」を作ることです。レコメンダーを活用すれば、プレイヤーのプレイスタイル、コミュニケーションの嗜好、プレイ時間帯、興味を持ちやすいトピックなどの情報を基に、相性の良いプレイヤーを見つけやすく��なります。特にチームベースのゲームでは、好んで使うキャラクターの種類なども考慮に入れることで、相性の良いチームメンバーと出会う機会を提供できます。
ゲームサーバーレコメンダー
ゲームサーバーの推奨は、通常は少数の変数(ping値、利用可能性、待機中のプレイヤー数、必要に応じて待機中プレイヤーのELO)で行われます。ほとんどのリアルタイム対戦型ゲームではこれで十分です。しかし、レイテンシーの重要度が低いゲームや、プレイヤーがサーバーに恒久的に割り当てられるケース、あるいはソーシャル要素の強いゲームでは、レコメンダーアプローチを検討する価値があります。レコメンダーを活用することで、互いに良い体験を共有できるプレイヤーを集めた、コミュニティ重視のゲームサーバーを構築するのが容易になります。
開発者の洞察:SciPlay
LiveOpsは、データの科学がタイミングと挑戦の芸術と出会うところです。それは、プレイヤーを意味のある体験でエンゲージさせつつ、疲労感やフラストレーションを避ける適切なバランスを保つことについてです。プレイヤーのセッションを自然に延長するように設計されたモデルを活用することで、プレイヤーがエンゲージメントを解除する可能性のある正確な瞬間を特定することは、彼らを没頭させ続けるためのちょうど良い体験を提供することを複雑にすることはありません。目標は単にコンテンツを追加するだけでなく、各インタラクションが個々のプレイヤーの体験に意��味を持つことを確認することでもあります。
ゲーム業界でのレコメンダーの構築
データ収集と準備
レコメンダーシステムがデータに大きく依存しているのは周知の事実です。では、どのようなデータが必要で、どの種類が最も有用なのでしょうか? データサイエンスの多くの事柄と同じく、答えは「状況次第」です。
レコメンダーの種類によって、最適化される目標、コンテンツの種類、ユーザー行動は異なります。「誰に」「どのような文脈で」レコメンドするかによって、必要とされるデータも変わります。例えば、プレイセッションの長さを延ばすために設計されたシステムと、マネタイズやソーシャルエンゲージメントの最大化を目的としたシステムでは、優先するシグナルが異なります。
とはいえ、ほとんどのユースケースに共通するデータ収集のテーマがあります。オンラインストアやIAP(アプリ内課金)のシナリオでは、購入行動が最も有用なシグナルの一つです。言い換えれば、「購入する」という行為自体が強力な暗黙的評価となります。同様に、ステージやマップ、その他のゲーム内体験をレコメンドする場合には、プレイヤーが「何をプレイしたか」「どのくらいの時間プレイしたか」「どのくらいの頻度で戻ってきたか」を追跡することが重要です。これらのイベントには必ずタイムスタンプを付与しましょう。時間の経過とともにプレイヤーの嗜好は変化し、新しいコンテンツが追加され、メタも変わるため、古いデータはモデルの性能を低下させる可能性があります。
暗黙的または明示的な評価に加えて、密な特徴量やカテゴリカルな特徴量もモデルを強化します。例えば、ESRB、PEGI、ELO などのレーティングは入力データや下流でのフィルタリングに役立つ場合があります。暴力表現、言語、性的表現といったコンテンツ属性もモデルに入力する有効な情報となります。
さらに、プレイヤーの文脈的なデータも考慮すべきです。典型的なプレイ時間帯、利用デバイスやプラットフォームの特性、位置情報などです。マルチプラットフォームタイトルでは特に重要であり、プレイヤーはモバイルでは短時間のセッションを好み、PCではより長く複雑なコンテンツを好む、といった嗜好を持っているかもしれません。こうした嗜好は、それぞれのシナリオで提示されるレコメンド内容にも反映されるべきです。
レコメンダー機能を支えるためには、企業としてデータを大規模に収集し、統合し、整理する必要があります。インサイトは、ゲーム内テレメトリー、ストアフロント、さらには Steam や Google Play ストアといった外部プラットフォームなど、複数のソースから得られます。そのため、ゲームにおいてはデータレイクハウスが適しており、レコメンデーションモデルのトレーニングやスコアリングのためにデータを取り込み、処理し、保存するための一元的な環境を提供します。これにより、プレイヤー体験を一段と引き上げることが可能になります。
モデルトレーニング
レコメンデーションシステムのモデリング手法や実装パターンは、ユースケースの数以上に存在すると��言っても過言ではありません。有名なNetflixのレコメンデーションモデルが登場して以来、この分野は学術界・産業界双方の大きな注目を集め、数多くの革新が生まれてきました。データ収集と同様に「万能の正解」はなく、最適なモデルアーキテクチャはユースケース、データ、そして目標によって完全に異なります。
そのうえで、大規模なオンラインゲームのように豊富な行動データがある場合は、最新のディープラーニングベースのレコメンダーが大きな効果を発揮することがあります。TorchRec は柔軟で実運用に耐えるフレームワークであり、多くのチームで効果的に活用されています。TorchRec における典型的な第1段階のアーキテクチャは「ツータワーモデル」です。これはユーザー(片方のタワー)とアイテム(もう片方のタワー)の埋め込みを生成し、それらを類似度検索に活用して、プレイヤーの嗜好とコンテンツをマッチングします。
ユーザー側のベクトルをアイテム側の埋め込み(ベクターデータベースに保存されている)と比較することで、最も関連性の高い上位10件のアイテムを高速で取得できます。これらはそのまま提示することも、プレイヤーと各アイテム間のクロス特徴を考慮する第2段階のモデルに渡して、より精緻なランキングやパーソナライゼーションを行うことも可能です。
簡単に言えば、このシステムは「ファネル(漏斗)」のように機能します。
すべてのアイテムカタログ��がファネルの上に存在する。
第1段階モデルで関連性の高いサブセットに絞り込む。
第2段階モデルでプレイヤーの文脈をより細かく考慮して再ランク付けする。
必要に応じて、年齢制限や文脈に基づく除外など追加フィルターを適用する。
これらのディープラーニングモデルのトレーニングには通常、GPUや分散コンピューティングが必要です。TorchDistributor や Ray Train といったツールが、複数ノードにまたがる並列トレーニングを管理するためによく使われます。前処理済みのデータは Mosaic Streaming や Ray Data などを用いてストリーミングできます。モデル選択やハイパーパラメータチューニングは、データのサブセット上で並列実行され、結果は検証用データセットで評価されます。
こうしたワークフロー(コード、指標、パラメータ、成果物を含む)の複雑さを管理するうえで、MLflow は極めて重要な役割を果たします。MLflow により、実験の追跡・比較・バージョン管理を一元化でき、チーム全体で「うまくいっていること」「次に改善すべきこと」を共有しやすくなります。
モデルのテストと評価
レコメンダーモデルのトレーニングが完了したら、その効果を評価すること��が重要です。評価は「モデル指標そのもの」と「プレイヤー体験やビジネス成果への影響」の両面から行います。通常、このプロセスには2つの段階があります。オフライン評価(デプロイ前) と オンライン評価(デプロイ後) です。
オフライン評価
オフラインテストは、モデルを本番環境に投入する前に実施し、過去のデータに対してどれだけ正しく機能するかを確認します。これはモデルが意図通りに動作しているかどうかを示す最初のシグナルとなります。代表的な指標には以下があります:
Precision / Recall(適合率/再現率):Top-K レコメンドにおいて、正しいアイテムが含まれているかを測定。
MRR(Mean Reciprocal Rank):ランキングの位置を重視。正解アイテムがどれだけ上位に表示されたかを評価。
NDCG(Normalized Discounted Cumulative Gain):ランキング指標の一つで、正解がリスト上位にあるほど高く評価。
RMSE / MAE:予測スコアや評価値を扱う際に使用(例:ユーザーがどれだけアイテムを楽しむかの予測)。
LLM生成の購買ペルソナ:推奨が全体的なペルソナにどれだけ関連しているかを測定。特定のユーザー群を継続的にテスト対象にすることで、時間をかけて複数のモデルを評価できる。
また、新規プレイヤー vs. 既存プレイヤー、モバイル vs. デスクトップ、低エンゲージメント vs. 高エンゲージメント といった異なるセグメントでテストを行うことも重要です。これにより、潜在的なバイアスや性能差を発見できます。
ただし、オフライン評価だけでは不十分であり、オンライン評価も必要です。
オンライン評価
モデルをデプロイした後は、オンラインテストによって実際のビジネスやプレイヤーへの影響を測定します。代表的な方法は古典的な A/Bテスト であり、高度な環境では マルチアームバンディット手法 なども用いられます。これは、新しいモデルを適用したユーザーとコントロールグループを比較することで行います。
A/Bテストで考慮すべき主な指標は以下のとおりです:
エンゲージメント:プレイヤーあたりのセッション数、セッション時間、次のセッションまでの時間。
コンバージョン:購入率、ARPU(ユーザーあたり平均収益)、バンドル選択。
リテンション:Day 1 / Day 7 / Day 30 のリテンション、コホートの減衰曲線。
プレイヤー満足度:間接的な指標(チャーン減少、ゲーム内チャットの感情傾向、サポートチケット件数の減少など)。」
よくある落とし穴
オフライン/オンラインの不一致:オフラインで高性能でも、本番環境ではドリフトや特徴不足、提供インフラの違いにより性能が低下することがある。
テストグループが小さすぎる:統計的有意差が出ず、結論が出せないまま時間を浪費する。
テスト期間が短すぎる:チャーン防止など一部の効果は長期的にしか現れないため、十分な追跡期間と忍耐が必要。
モデルのデプロイメントと推論
レコメンデーションモデルを構築し、関係者が初期評価に満足したら、いよいよ本番環境へのデプロイの段階です。これは通常、複数のアプローチを組み合わせたプロセスになります。具体的には、オフラインスコアリングによって事前に推奨アイテムを計算しプレイヤーに提供できるようにしておく方法(バッチまたはストリーミングモード)、あるいは常にその場で結果を計算するオンラインスコアリングがあります。
Databricks はこれらのシナリオをどちらも強力かつ効率的にサポートしており、バッチ処理やストリーミングに加えて、オンラインモデルサービングを通じて同じモデルを提供することも可能です。さらに安心なのは、これらすべてのアプローチが Unity Catalog によって統一的にガバナンスされる点です。モデルはテーブル、関数、ファイルなどと同じように Unity Catalog に登録され、バージョン管理やアクセス権限などガバナンスに必要な要素が揃っているため、チームは一貫性のあるセキュアな環境で開発・運用を進められます。
モデルがカタログに登録されると、下流のパイプラインから参照できるエイリアスが付与されます。これにより常に最新の公開済みモデルを利用できます(例:models:/production.personalization.two_tower_item_recommender@champion)。
特徴量テーブルも同様にデプロイされます。特徴量エンジニアリングクライアントを用いてモデルを公開すると、すべての特徴量ルックアップや変換関数がメタデータとして自動的に記録されます。したがって、下流のチームはユーザーキーとタイムスタンプを指定するだけで推奨結果を取得でき、その他は特徴量エンジニアリングライブラリが処理してくれます。さらに、モデルはバッチやストリーミングと同じソースを利用してオンラインサービングエンドポイントにデプロイまたはアップグレードできるため、�すべての推論経路に一貫性が保たれます。
モデル監視
レコメンダーはどこに組み込まれていてもビジネス指標全体に影響を与えるため、オフラインでの評価以上にオンライン評価の能力が重要です。トレーニング時にRMSEのスコアが良かったとしても、実際に運用した際に売上やレビュー、その他の指標を悪化させるのであれば、その問題を即座に把握する必要があります。そのため、複数の測定戦略を採用し、A/Bテストのようなデプロイ技術と組み合わせるのが一般的です。
「@champion」エイリアスと同様に、「@challenger」エイリアスを付けたモデルをデプロイし、実際のユーザーやビジネスへの影響を確認するために一部のトラフィックを振り分ける、といった運用も可能です。Databricks が提供する Lakehouse Monitoring を利用すれば、データや時系列テーブル、推論結果テーブルに関する統計やドリフト指標を収集・監視できます。これにより、チームはこうした変化を継続的に測定・追跡し、レコメンデーションシステムを通じて実際のビジネス成果を達成することができます。
Databricksを使ってゲームをより直感的にする
どのようなタイプのゲームを開発している場合でも、レコメンダーはプレイヤー中心の体験を構築するうえで非常に大きな可能性を秘めています。
レイクハウスを基盤とする統合データプラットフォームの上に構築することで、大量かつ多様なデータソースから得られるインサイトを活用したレコメンダーを作成できます。これに��より、プレイヤーやその嗜好、ゲーム内での体験を包括的に把握できるようになります。一方、レイクハウスがなければ、プレイヤーに関する重要な情報が欠落し、不十分なレコメンデーションにつながる可能性があります。
データプラットフォームがなければ、チームは実用的なインサイトを生み出すよりも、接続性や基盤となる技術ツールの管理に時間を取られてしまいます。朗報として、レコメンダーは進化を続けており、その有効性をさらに高める新しい機械学習機能も開発されています。MLOps、A/Bテスト、成果のトラッキング、新しいモデルの本番デプロイ を可能にするデータプラットフォームは、いまや不可欠です。
さらに、そのプラットフォームには、会話型アナリティクスによる容易な特徴量エンジニアリングや、Unity Catalog によるガバナンスとデータリネージ基盤を通じたインサイトへの信頼性確保といった機能も備わっている必要があります。Databricks は、ゲーム企業がコスト効率よくレコメンデーションシステムを調査・構築・テスト・本番デプロイできるよう支援します。
これらのユースケースやその他の活用方法について詳しく知りたい方は、databricks.com/games をご覧いただくか、担当のアカウントエグゼクティブまでお問い合わせください。また、データ・AI・ゲームに関する詳細は、弊社のeBookやソリューションアクセラレータからも学ぶことができます。